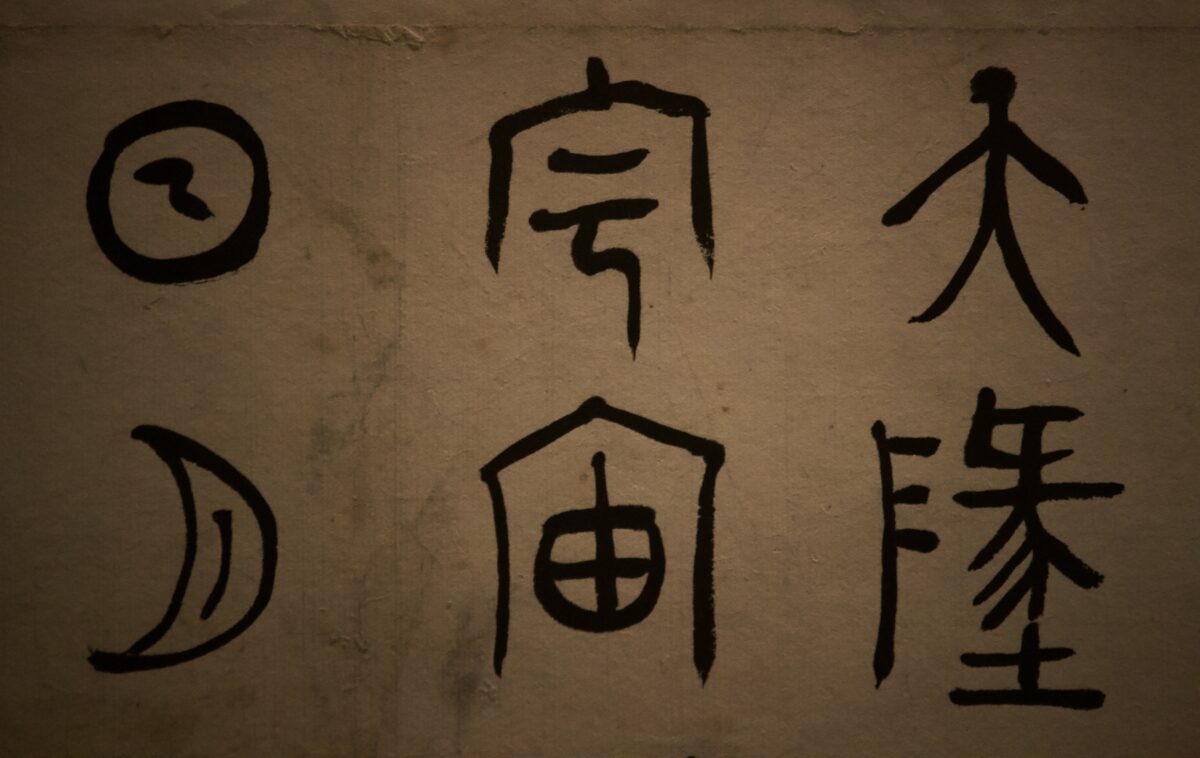今回はNetflixで配信中の朝鮮王朝を舞台にしたドラマ『恋慕(原題:연모)』に登場するちょっと難しい専門用語をまとめてみました。李氏朝鮮時代の社会構造や役職・階級などを表す現在では使われない単語が多い為、外国人向けの韓国語単語テキストにも載っていませんが、ドラマを観てストーリーを理解する上で助けになればと思います!
-

【韓国ドラマ名鑑】恋慕(2021)結末ネタバレあり
続きを見る
『恋慕』とは
双子の妹として生まれながらも、双子をよしとしない王命で殺されそうになり、宮廷の外で捨て子として育てられたタミだが、幼かったある日自分とそっくりの世子(王位後継者)と遭遇し、彼の身代わりをするようになるが、タミが生きている事を嗅ぎつけた王族の策略でタミと間違えて本物の世子が殺されてしまい、タミが世子として男装して生きていく事になってしまう。10年後、男になりすまして立派に成長した世子の前に師匠として現れたのは初恋の相手チョン・ジウンだった。決して打ち明けられる事のな恋心や宮廷内の対立を描いたフュージョン時代劇。

| 原題 | 연모 |
| 英語タイトル | The King's Affection |
| 視聴者の間で使われる略称 | |
| ジャンル | 時代劇、ロマンス |
| 放送時期 | 2021年10月11日〜12月14日 月火21:30〜 |
| 放送局 | KBS2 |
| 演出 | ソン・ヒョノク 「また!?オ・ヘヨン」「ビューティー・インサイド」など イ・ヒョンシク 「こんにちは?私だよ!」など |
| 脚本 | ハン・ヒジョン 「朝鮮ガンマン」「とにかくアツく掃除しろ!?~恋した彼は潔癖王子!?~」など (原作:イ・ソヨン『恋慕』) |
| 最高視聴率 | % |
| 話数 | 20話 |
| 視聴等級 | 15歳以上 |
| 公式サイト | 番組ホームページ |
| 筆者オススメ度 | ★★★★★ |
| タミ 宮廷で双子の妹として生まれるも殺されそうになり、嬪宮の計らいで宮の外に出されたが、運命の悪戯で宮女となり自分と瓜二つの兄で世子であるフィと再会する。 イ・フィ(世子) 王位継承者。偶然出会った瓜二つのタミを双子の妹と知らないまま外出中の身代わりを頼むようになるが、タミを殺そうとする外祖父の策略でタミの代わりに殺されてしまった。 | パク・ウンビン 「青春時代」「ブラームスが好きですか?」など (子役:チェ・ミョンビン) 「梨泰院クラス」「ボイス4」など |
| チョン・ジウン タミの初恋の相手で、明に留学した後に書筵官(世子に学問を教える師匠)としてやって来る。 | ロウン SF9のリードボーカル。 「偶然見つけたハル」「先輩、その口紅塗らないで」など (子役:コ・ウリム) 「あなたが眠っている間に」「この恋は初めてだから」など |
| イ・ヒョン(チャウン君) 世子の従兄で実の兄のように育てられた。ジウンとも幼い頃からの親友である。何かを知っているかのように切ない眼差しで世子を見守るが…。 | ナム・ユンス 「人間レッスン」「怪物」など |
| キム・ガオン ある日、大妃の命を受けて世子の護衛として派遣された剣士。何か裏があるようだが…。 | チェ・ビョンチャン VICTONのサブボーカル。 「Live On」など |
| シン・ソウン 吏曹判書の娘。ある日謎の発疹に悩まされてジウンが営む医院に押しかけ、ヨンジを人質に取るなど強気に出るがジウンに惹かれてしまう。 | ペ・ユンギョン バラエティ「ハートシグナル」、「青春記録」など |
| ノ・ハギョン 兵曹判書の末娘。 | チョン・チェヨン DIAメンバー。I.O.I元メンバー。 「初恋は初めてだから」シリーズなど |
| ハン・ギジェ 左議政。嬪宮の父でフィからは母方の祖父(外祖父)にあたる。王とは水面下で対立していて権力を狙っている。 | ユン・ジェムン 「スリーデイズ〜愛と正義」「ラスト」など |
| チョン・ソクチョ 執義。ギジェの腹心でジウンの父。ギジェの命令でタミやタミを知る人物を襲うが、その場面をジウンに目撃されてからは親子の関係が崩れてしまった。 | ペ・スビン 「華麗なる遺産」「トンイ」など |
| ヘジョン フィとタミの父で現王(※歴史には登場しない架空の人物)。嬪宮の死後、継妃を娶った。 | イ・ピルモ 「ピノキオ」「ヘチ 王座への道」など |
| キム尚宮 東宮の女官で世子の身の回りの世話を任されている。世子が女性であるという秘密を知る数少ない人物。 | ペク・ヒョンジュ 「ザ・キング:永遠の君主」「椿の花咲く頃」など |
| ホン内官(ボクトン) 東宮に仕える内官でフィの最も近い臣下であり、幼い頃タミとフィが入れ替わっている間も口裏を合わせていた事から世子の秘密を知る数少ない人物。 | コ・ギュピル 「愛の不時着」「バガボンド」など |
| パン・チルグム 三開房で働くジウンの親しい仲間でお調子者。ヨンジの兄。 | チャン・セヒョン 「スタートアップ:夢の扉」「花郎」など |
| パン・ヨンジ 兄とともに三開房で働く娘。強気だが、事あるごとに人質として囚われてしまう。 | イ・スミン 「アビス」「逆賊ー民の英雄ホン・ギルドンー」など |
| 大妃 フィとタミの祖母。世子に愛情を注ぐが自らの勢力も保つ強さも見せる。 | イ・イルファ 「応答せよ」シリーズ「彼女の私生活」など |
| 嬪宮 フィとタミの母親。ある日危険が及ばないように宮廷の外に捨てたタミが宮中にいる事を知ってショックを受けるが、フィが殺された後はタミに世子として生きていくようしつける。その後間もなく病に倒れこの世を去った。 | ハン・チェア 「内省的なボス」「客主〜商売の神〜」など |
| 王妃 王の継妃。自らが産んだジェヒョン大君を王にすべく、世子や左議政と水面下で対立する。 | ソン・ヨウン 「3度結婚する女」「復習のカルテット」など |
| チャンウン君 世子の叔父。身分をひけらかして酒に溺れ、世子を陥れようとするなど悪事を働く。 | キム・ソハ |
| ジェヒョン大君 世子の腹違いの弟(後妻の子)。 | チャ・ソンジェ 「愛の不時着」など |
用語集(50音順)
あ行
| 아바마마(アバママ) | 宮廷内で王族が自分の父を呼ぶ際の呼び名。日本語に訳すと「父上」。 |
| 安置刑(アンチヒョン) | 流刑の一種で、遠い場所に送られ住居を制限される刑罰。王族や高官に適用された。 |
| 禮部侍郎(イェブシラン) | 明の六部の一つとして典礼・祭事・教育・科挙・外国特使・使臣・来賓客応対などを行っていた機関。 |
| 芸文館(イェムングァン) | 国王とその周辺の動静の記録や議事録の作成を行う機関。 |
| 翊衛司(イグィサ) | 1418年に設置された兵曹の所属機関で世子の護衛(世孫もいる場合世孫も)を担当した官庁。武術に長けた者で構成された。 |
| 二刻(イガク) | 30分の事。 |
| 翊善(イクソン) | 世孫講書院に属し、王世孫の教育を担っていた正四品の位。 |
| 吏曹判書(イジョパンソ) | 国政を担当する六つの曹のうち、文官の人事を担当していた役人の長官。現代日本の総務省に該当する。 |
| 吏曹銓郎(イジョチョルラン) | 国政を担当する吏曹の正五品の官職に就く3人と佐郎(正六品)3人の総称。王に直言できる三司を推薦する権限も持つ。 |
| 日官(イルグァン) | 天文観測や吉凶を占う観象監の役人。 |
| 義州(ウィジュ) | 古来より朝鮮半島の西北の関門であり、明代・清代の朝鮮王朝の使節は義州と九連城の間で鴨緑江を渡渉していた。平安道の中心の一つであり、1895年には現在の平安北道一帯を管轄する義州府が置かれた。 |
| 義興衛(ウィフンエ) | 略称は中衛(チュンウィ)。京畿道、慶尚道、全羅道を警備していた政府軍。 |
| 外祖父(ウェジョブ) | 母方の祖父(時代劇以外でも使われる)。 |
| 御医(オイ) | 王の主治医。 |
| 五台山(オデサン) | 大韓民国北東部の江原道にある山並の総称。朝鮮半島東部を貫く太白山脈の一部をなす。 |
| 温陽(オニャン) | 現在の牙山市。かつては温陽郡と呼ばれていた。 |
| 어마마마(オマママ) | 宮廷内で王族が自分の母を呼ぶ際の呼び名。日本語に訳すと「母上」。 |
| 오랑캐(オランケ) | 北方に居住する異民族の一部を称していた。モンゴルのウリャンカイ部とは無関係な女直の一派で、明朝からは野人女直、清朝からは東海三部と称された集団の一つ、ワルカ部に相当する集団である。 |
か行
| 갓(カッ) | 両班が被る黒い帽子。 |
| 家和万事成(カファマンサソン) | 家が平和であってこそ何事も上手くいくという諺。 |
| 甘紅露(カモンノ) | 朝鮮半島の伝統酒で米焼酎に生姜や甘草、桂皮、龍眼肉などの韓薬を漬け込んだもの。 ドラマではジウンを意識して頬を赤らめた世子に対して「頬が甘紅露の様に赤い」と比喩で使われました。 |
| 嘉礼(カレ) | 王族の結婚を祝う儀式。 |
| 講書(カンソ) | 書物の内容を講義する事。 |
| 康寧殿(カンニョンジョン) | 王が読書と急速、臣下たちとの議論を交わした空間。 |
| 江華(カンファ) | 現在の仁川広域市にある。江華都護府が置かれ、その後江華府・江華留守府に昇格して、重要な位置を占め続けた。 |
| 講武場(カンムジャン) | 武術の訓練を行う場所。 |
| 瓜田不納履(クァジョンプルナムニ) | 「瓜田に履を納れず」疑われるような事は避けろという諺。本来は瓜田不納履 李下不整冠と言い、「瓜田で履物を履き直したり、スモモの木の下で帽子を直す仕草が野菜や果実を盗んでいるように見えてしまうから疑われないように慎め」という意味です。 |
| 観象監(クァンサンガム) | 天文や風水、暦や気象観測などを司っている役職で、王と王妃の床入りに縁起のよい日付も助言した。 |
| 揀択(クァンテク) | 李氏朝鮮で王室の女性となる者(王妃、世子嬪など)を選ぶ行事。世子より少し年上の両班の女性は必ず候補者として申告せねばならず候補者は名門出身で、父親の地位はあまり高くなく、権力も財産も持たないのが望ましいとされた。 |
| 闕(クォル) | 宮中を示す言葉。 |
| 捲堂(クォンダン) | 成均館の学生が示威行動(デモ)を行う事。 |
| 九節草(クジョルチョ) | 和名はイワギク。九節草は風が良く通る場所で太陽の下で干して薬として使われた。 |
| 勤政殿(クムジョンジョン) | 李氏朝鮮の王宮である景福宮の中心部にある正殿。 |
| 宮女(クンニョ) | 幼い頃から宮廷に住み込み王族に仕える女性。正一品から従四品までが王の側室に与えられる階位で、正五品〜従九品までが王宮で働く労働階層だった。王族の身の回りの世話をしつつ、気に入られれば側室となる可能性もあった為、恋愛や結婚は禁止されていた。 |
| 妓生(キーセン) | 諸外国からの使者や高官の歓待や宮中内の宴会などで楽技を披露したり、性的奉仕などをするために準備された奴婢の身分の女性(「婢」)。最上の者を一牌 (イルペ)、次の者を二牌 (イペ)、最も下級な者を三牌 (サムペ) と呼んだ。 |
| 妓楼(キル) | 芸妓や遊女を置いて客に遊興させることを業とする施設。 |
| 科挙(クァゴ) | 朝鮮王朝で官吏を選ぶ為に行われた試験制度。官吏に登用されてこそ出世することができた当時には、官吏の任用制度としての科挙が大きく注目された。 |
| 고뿔(コップル) | 風邪の事。 |
| 乾地黄(コンジファン) | 韓方で使われる薬草の一つ。アカヤジオウの根を乾燥させたもの。 |
| 建春門(コンチュンムン) | 景福宮の東門。 |
さ行
| 司諌院(サガンウォン) | 李氏朝鮮における官府。朝鮮王に諫言し、政治の非を論駁する職務を管轄する。官職は正三品の大司諫、従三品の司諫、正五品の献納、正六品の正言がある。 |
| 四知(サジ) | 「後漢書」の楊震伝より。天・地・自身・相手が既に知っていて、どんな秘密もいつかは他に漏れるという意味。 |
| 社稷(サシク) | 古代中国において社(土地神)と稷(穀物神)の総称。転じて国家そのものを示すようになった。 |
| 使臣団(サシンダン) | 君主や国家の命令を受けて、外国などに使いをする人。大使、公使などの類。 |
| 司憲府(サホンブ) | 時政の論評、官吏の糾察、褒挙、風俗の矯正、冤抑の解決などに関する業務を管掌していた政府機関。 |
| 司書(サソ) | 世子の教育にあたる侍講院の役職の一つで正六品に該当する。 |
| 尚宮(サングン) | 朝鮮時代の宮官のひとつ。内命婦に属する正五品の女官。国王の事実上の側室である四品の下では最も位が高い。 |
| 産室庁(サンシルチョン) | 宮中の出産を取り仕切る機関。 |
| 上疏(サンソ) | 事情を王に陳述する事。 |
| 尚膳(サンソン) | 宮中の雑用を取り仕切る機関である内侍府に働く役職で、判内侍府事、大殿内官とほぼ同じ。 |
| 常参(サンチャム) | 宮中での朝の集い。 |
| 上王(サンワン) | 譲位した国王に対する尊号。太上王(テサンワン)ともいう。 |
| 侍講院(シガンウォン) | 世子の教育にあたる機関。 |
| 弑逆(シヨク) | 臣下が君主を殺す行為、またはそれを実行する者。 |
| 神武門(シンムムン) | 景福宮の最北にある門。現在の門の向かい側には大統領官邸である青瓦台がある。 |
| 水刺(スラ) | 王の食事。 |
| 水刺間(スラッカン) | 王の食事を調理する場所。 |
| 承政院(スンジョンウォン) | 王の身の回りの世話を管轄する宮内庁に該当する機関。 |
| 承政院日記(スンジョンウォニルギ) | 王の行動を記録した書物。 |
| 世子(セジャ) | 王位継承者。 |
| 世子冊封(セジャチェクポン) | 朝廷の承認を得て更に中国の皇帝からの許しを得て世子として認められる事。 |
| 世子嬪(セジャピン) | 王位継承者の正妻。 |
| 世孫(セソン) | 王位継承者の子で次の次の王位継承者。 |
| 生果房(セングァバン) | 生果、熟実果、煎果、茶食、粥など王と王妃のデザートと特別メニューを準備していた場所。 |
| 束脩(ソクス) | 入学・入門の際に弟子・生徒が師匠に対して納めた金銭や飲食物などの贈り物。 |
| 蘇朗草(ソナンチョ) | 毒草。 |
| 璿源殿(ソヌォンジョン) | 歴代王や王后の肖像画を祀る施設。 |
| 西廡(ソム) | 中庭の西側の建物。東廡と対称をなしている。 |
| 庶尹(ソユン) | 朝鮮王朝時代、首都の行政や司法等を担当した官庁の従四品。 |
| 書筵(ソヨン) | 書物などの講義。 |
| 書筵官(ソヨングァン) | 書物などの講義を行う講師。 |
| 瑞麟坊(ソリンバン) | 漢城中部にあった地名。 |
| 成均館(ソンギュングァン) | 李氏朝鮮の最高教育機関。 |
| 孫子の兵法(ソンジャビョンポプ) | 中国で古くから伝わる兵法。紀元前500年頃の春秋時代の軍事思想家である孫武の作が起源であると言われている。 |
| 선비님(ソンビニム) | 学識が優れて礼節があって義理と原則を守って権力と富裕栄華を貪らない高潔な人柄を持った人に対する両班層の理想像を指す用語。 |
た行
| 端午節(タノジョル) | 端午の節句。 |
| 提調(チェジョ) | 従一品、正二品、従二品までの3つの官位を指す。 |
| 執義(チブィ) | 司憲府の従三品にあたる役職。 |
| 左議政(チャウィジョン) | 朝鮮時代の副首相に該当する役職。 |
| 慈慶殿(チャソンジョン) | 先王の妃である大妃の暮した寝殿。 |
| 資善堂(チャソンダン) | 世子夫婦の生活空間。 |
| 昌徳宮(チャンドックン) | 1405年に正殿である景福宮の離宮として創建され、景福宮が焼失してから再建までは正殿としても使われた宮殿。ソウルに現存するものは1623年に再建されたものだが最も創建時の面影を残している。 |
| 注書(チュソ) | 宮内庁に該当する承政院の正七品を指す。 |
| 中宮殿(チュングンジョン) | 王妃のプライベートな空間。 |
| 切頭山(チョルトゥサン) | 現在の漢江北岸麻浦区合井洞にある小高い山。かつての名称は蚕頭峰(チャムドゥボン)。 ※1866年にここでカトリック信者が迫害されて斬首された事からこの名が付いたのでドラマの作中の時代に切頭山と呼ぶのはおかしな設定です。 |
| 正郎(チョンナン) | 六曹の組織内での正五品を指す。 |
| 春秋左氏伝(チュンチュジャッシジョン | 孔子の編纂と伝えられている歴史書『春秋』の代表的な注釈書の1つで、紀元前700年頃から約250年間の魯国の歴史が書かれている。 |
| 漕運船日誌(チョウンソニルジ) | 兵料の運送に関する船の日誌。 |
| 宗鏡録(チョンギョンノク) | 中国五代十国時代の呉越から北宋初の僧の永明延寿が撰した仏教論書、100巻。 |
| 宗親(チョンチン) | 宗室に属する王族。 |
| 宗簿寺(チョンブシ) | 王室の族譜である璿源譜牒を記録・調査する機関。 |
| 賎民(チョンミン) | 階級制度のうち最底辺に位置した。 |
| 進士(チンサ) | 科挙の登第者(合格者)。 |
| 大監(テガム) | 官職のうち正一品~正二品の間の官職を持つ者。王と直接議論する事が許され、赤い官服を着た。 |
| 大司憲(テサホン) | 司憲府のトップに位置する官職。 |
| 大提学(テジェハク) | 弘文館の官職のうち正二品を指す。 |
| 大殿(テジョン) | 国王の住む宮殿。 |
| 胎室(テシル) | 王族の子孫のへその緒を祀る場所。 |
| 大妃(テビ) | 先王の妃。 |
| 大妃殿(テビジョン) | 先王の妃が暮らす区画。 |
| 太平館(テピョングァン) | 明国の使者をもてなすため、接待した宿所。迎賓館。 |
| 都承旨(トスンジ) | 王命の伝達を担った承政院に属する六つの官職(承旨)の一つ。最高責任者。吏曹への連絡も担当していた。 |
| 도련님(ドリョンニム) | 幼い男性に対する尊称。「お坊ちゃま」。 |
| 東宮(トングン) | 世子の居所。 |
| 東宮殿(トングンジョン) | 世子の居所である施設。 |
| 通字栍(トンジャセン) | 試験における最も高い成績。 |
| 東氷庫(トンビンゴ) | 王室で使う氷を保存していた官庁の倉庫のうち、儀式に使う氷を扱っていた倉庫。 |
| 東廡(トンム) | 中庭の東の建物。西廡と対称をなしている。 |
な行
| 나으리(ナウリ) | 官職のうち正三品堂下官以下の者。正三品堂下官以下~従六品は青い官服・正七品~従九品は緑の官服を着た。 |
| 納幣書(ナッペソ) | 結納品とともに送る婚姻の証明書。 |
| 男色(ナムセク) | 男性同士の同性愛を示す言葉。 |
| 朗君(ナングン) | 年若く身分の高い男子や主家の息子を敬って呼ぶ言葉。 |
| 奴婢(ノビ) | 階級制度のうち賎民に属し、一般的に職業選択の自由、家族を持つ自由、居住移転の自由などが制限されていた。 |
| 内医院(ネウィウォン) | 王族や宮中の医療に関わる機関。 |
| 内官(ネグァン) | 王や世子の側近として世話をしていた男性で。去勢(睾丸を切除)している事が求められる。 |
| 内禁衛(ネグムィ) | 李氏朝鮮における、王室を護衛する軍営。 |
| 内禁衛将(ネグムィジャン) | 内禁衛に属する官職の一つ。 |
| 内帑金(ネタングム) | 君主が所持する金。 |
| 内命婦(ネミョンブ) | 朝鮮時代に宮中で公務に就いた女官の総称。内命婦は、最上位に王妃・世子嬪(皇太子妃)、正一品から従四品までの国王側室の内官、正五品の尚宮から従九品までの宮中の仕事を処理する女官である宮官に大別された。 |
| 論語注疏(ノンノジュソ) | 『論語』に付された注釈。 |
は行
| 漢陽(ハニャン) | 現在のソウル。 |
| 咸吉道(ハムギルド) | 現在の北朝鮮・咸鏡道。 |
| 할바마마(ハルバママ) | 宮廷内で王族が自分の祖父を呼ぶ際の呼び名。 |
| 할마마마(ハルマママ) | 宮廷内で王族が自分の祖母を呼ぶ際の呼び名。 |
| 漢城(ハンソン) | 現在のソウル。 |
| 漢城府(ハンソンブ) | 朝鮮,李朝の首都(ソウル)を管轄した官庁。 正二品衙門として国王に直属した。 行政範囲は城内5部と城外10里。 |
| 批答(ピダプ) | 王が国民や官吏の請願に答える事。 |
| 丕顕閣(ビヒョンガク) | 世子が日常業務を行っていた所。 |
| 平安道(ピョンアンド) | 現在は北朝鮮側に位置する半島北西部の道。 |
| 便殿(ピョンジョン) | 王・王后、王子、王妃が休息する為に建てられた御殿。 |
| 嬪宮(ピングン) | 世子の正妻。 |
| 華陀(ファダ) | 中国,後漢末期の伝説的名医。 とくに外科にすぐれ,麻沸散という麻酔薬を用いて,開腹手術や脳手術をしたといわれる。 |
| 黄連(ファンリョン) | 韓方で用いられた薬草の一種。オウレンの根を乾燥させたもの。 |
| 会講(フェガン) | 毎月、世子や世孫の教育の進み具合を確かめる為に行われた試験。 |
| 符節(プジョル) | 石や玉で作られた割り符。 |
| 不消花(プソファ) | 毒草。摂取すると腹部が膨張し歯茎が黒ずみ即座に現れる。 |
| 副護軍(プホグン) | 五衛と呼ばれる警備機関の従四品の官位の呼称。 |
| 不字栍(プルジャセン) | 試験で最も低い成績となる事。 |
| 不飛不鳴(プルビプルミョン) | 鳥が鳴かず飛ばず誰かを待ち続けているという言葉。 |
| 廃世子(ペセジャ) | 世子の位を廃位する事。 |
| 烹刑(ペンヒョン) | 熱くない釜に入れて出た瞬間から死んだ扱いにする名誉刑。 |
| 伏魔殿(ポンマジョン) | 悪が救う場所。中国の『水滸伝』に登場する。 |
| 戸曹(ホジョ) | 戸口、貢物、田糧、租税、食糧および国家財政に関連した部分を担当した。 現在の企画財政部に相当する。 |
| 벗(ポッ) | 友人を表す古語。 |
| 輔德(ポドク) | 世子の教育にあたる侍講院の役職の一つで従三品に該当する。 |
| 本草綱目(ポンジョガンモク) | 中国の本草学史上もっとも分量が多く内容が充実した薬学著作。1578年に完成したと言われている。 |
| 婚談(ホンダム) | 良家同士の縁談。 |
| 弘文館(ホンムングァン) | 王の諮問に応えたり、宮廷内の蔵書を管理、政策等の草案作りを担当した機関。 |
ま行
| 마님(マーニム) | 位の高い夫人を呼ぶ際の呼称。 |
| 問安診候(ムナンジヌ) | 5日毎に行われる王の健康診断。 |
や行
| 両班(ヤンバン) | 由緒ある家柄である文班と武班を合わせた名称で世襲制の為、罪を犯さない限り親から子へと継承される。 |
| 楊花津(ヤンファジン) | 現在の漢江北岸の麻浦区合井洞付近。 |
| 儒生(ユセン) | 儒教を自らの行為規範にしようと儒教を学んだり、研究・教授する人。 |
| 連環計(ヨヌァンゲ) | 孫子の兵法第35計。複数の計略を同時に利用する戦略。 |
| 閭延(ヨヨン) | 咸吉道(威鏡道)の鴨緑江上流部にあたり、北方からの女真族の襲撃を受けた。後世に廃四郡と呼ばれた。 |
| 領議政(ヨンウィジョン) | 朝鮮時代の宰相。 |
| 令監(ヨンガム) | 官職のうち従二品~正三品堂上官の間の者。王と直接議論する事が許され、赤い官服を着た。 |
| 延辺(ヨンビョン) | 現在は北朝鮮北東部の咸鏡北道の辺り。古くから中国との国境地帯となってきた。 |